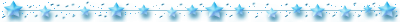
Novel Next
前編
海の中だった。
目の前を、何故か仏頂面で長い髪の少女が歩いていた。
やけに綺麗なシルクっぽい服を着て、耳には蒼い石のピアス。
顔は、もろに俺の親父の若い頃のものだった。
……ナゼ。
取り敢えず自己紹介。
俺の名は、ナイト。ナイト=ツウォイル、17歳。綴りは騎士[Knight]ではなく、夜[Night]だ。
人魚と『祝福の子』である、王位継承権を持たない王子の間に生まれた息子だったりする。
ま、両親の恋のエトセトラはおいといて、そんなわけで水中でも陸上でも呼吸が出来る。んでもって、水中ではモロ人魚の下半身であるのが恥ずかしい。でも、潜るのは好きだ。
で、休暇で海辺の別荘に来て、幼い頃から気に入ってた絶交の潜りポイントに来た。
従兄弟のサイハもいないし、て言うか潜れないし、一人で海の中を満喫する予定だった。
なのに、目の前に、親父の、見た事はないけど若い頃の顔をした少女が一人。しかもナイスバディ。
親父は割に中性的な顔をしてるからまあ見る分には耐えない。けど、そんな問題じゃねぇ!
母さんにベタ惚れな親父に隠し子なんていねえ! しかもどうしてヒレも生やさず歩いてんだよ!?
その内そいつがこっちを向いた。そして少し目を見開いて、
「……誰だ」
いやそれこっちのセリフだから。
「そっちこそ、誰だよ。何でうちの親父の顔してるんだ」
「ウェイルディーナ=セリフィリア。海神の娘。貴様が、『三界の命』の息子か」
俺の全身を見渡しながら彼女が告げる。サンカイノメイ? ワダツミ?
「お前の父が落とした命を貰い受けて、この世に生を得ている。さあ、これでいいか」
「良くないよ。まあいいか。後で詳しい事情は聞かせて貰う。俺はナイト=ツウォイル」
「ナイトか。では、七の姫と『三界の命』に取り次ぎを願おう」
尊大に彼女が言った。
*
「ぅぎゃあ、俺がもう一人! 女だし!?」
彼女を別荘に案内すると、庭にいた親父が予想通りの反応をした。母さんは、
「セリフィリアって言えば海神の!? きゃー、可愛い! 昔のルイトよルイト!」
なんて言って感激している。
「『三界の命』。貴方が」
「うん? 『三界の命』? 俺は『祝福の子』だけど」
首を傾げた親父に、眉一つ動かさずに、
「人間共はそう言います。天界、海界、陸界。その三界の命を持っている、だから『三界の命』」
ウェイルディーナが解説する。
「私は昔大病を患った。そして、丁度その時に貴方の命が海に帰った。だから、それを使って病を治しました。
そして、このようなツラに」
ツラってあんた。
「あのさ、最初からそう説明してくれね?」
「面倒くさかった」
「はあ!?」
面倒だと!? しかも、どうして俺にはタメ口!?
「で、どうしてその貴方が此処にいるの?」
母さんが近寄ってきて目を輝かせて問う。
「従兄弟と結婚させられそうになったから逃げてきました」
簡潔だった。内容は重かった。
「はあ!?」
「迷惑はかけません。少しの間で良い、此処においてくれませんか」
俺の事は完全無視。
すっごくむかつくんですけど。
*
迷惑は本当にかけられなかった。どうも細工の腕はあるようで、そこらの流木やら糸やら石やらを使って、魔法の如く綺麗なものを作り上げていき、それを売る。なかなかの稼ぎになった。
その作業が終わるといつも母さんに髪型やら、何やらをいじられていたりする。俺とは滅多に話さない。
母さんの言う所に寄ると、海神というのは海を司る数名の神様達の事で、ウェイルディーナはその首領・ポセイディンの娘さんらしい。早い話がかなり高貴な身分なのだそうだ。ポセイディンなんて、お伽話でしか俺は知らなかったけれど。
海界には生命を司る性質もあるらしく、父さんの命は海で落とされたから海神の手に渡ったらしい。
因みに地上で死ねばランダムに天界と海界に命が渡る。稀に地上のどっかへ行くのもあるんだとか。
で、どうして父さんがあんな変な体質であるか、ウェイルディーナは食卓で話していた。
昔、一人の海神と一人の空の神が恋をしたらしい。彼らは結局どちらの世界も追われ、地上に降りた。
そこで子供を作ったが、その子供は天、地、海、三つの世界で与えられるはずだった命を全て持っていた。
だから、三つ命がある。そして、その子供を含めその子孫は、『三界の命』と呼ばれる、という事だった。
*
そんな事を思いだしながら、夕暮れの海岸を俺は歩いていた。もう空の紅は紫となっている。
手の平に、俺が生まれた時に握っていたという石を弄ぶ。ただの石だが、何故かとても落ち着く、蒼い石だ。
あいつの言う通りだとすれば、俺の体質の意味が分からない。
俺は『三界の命』じゃあない。けど、『三界の命』と同じ様な扱いを受けた。
ふと前に目をやると、此処に来て四日になるウェイルディーナが砂浜にたたずんでいた。
「……何してるんだよ」
まさか初日の無視返しをするわけにも行かず、声をかける。
「……ナイトか」
「ここがいくら別荘地って言ったって、日が暮れたら物騒だぞ」
「うむ」
「……なあ、お前さ、どうして俺と話そうとしないんだよ」
ずっと抱えていた問いだ。話そうとする機会は幾らでもあったのに、どうして。
逆に気になるんだ。そんな事されると。
「そう、だったか?」
自分でも気付いていなかったらしく、本気で呆気にとられたような顔で返され、気が抜けた。
「そうだよ。俺だけタメ口だし」
「……歳が同じぐらいだったから」
歳、と言ってもなあ、神様だしなあ。……たぶん外見で判断すべきなんだろうな、こいつらの『歳』とやらは。
そうだったか、そう見えたか、と呟きながらウェイルディーナが長い髪を掻き上げた。しなやかで美しい髪がその手から零れ落ちる。
「大体お前、海の近くにいて良いのか? 相手は海の神様だろ」
「大丈夫だ。水には触れんし、触れても感づかれぬだけの力はある」
「………」
それでも、早く内陸に逃げた方が良いんじゃあないか?
俺の顔から考えを読み取ったらしく、ウェイルディーナはクスリと笑う。
間違っても嫌みではない、純粋な笑みだった。
「海が恋しくなるからな、どうしても」
「それで離れられないってか」
「ああ」
そのまま、沈黙が過ぎた。
なんにも話せないっての。何話しゃあ良いんだよ。
ああ、そうだ。名前だ。
「ディーナって呼んで良いよな。長ったらしい、覚えにくい奴じゃなくて」
「・・・ああ」
軽く豆鉄砲を喰らったような顔をして、ウェイルディーナ、いや、ディーナは頷く。
「俺の事は、ああ、ナイトって呼んでるか、もう」
「うん。……もうすぐお前の時間か」
夜。海に潜れば常闇、そして時々の美しい光を見せる時間。
「俺の時間……って程大それたもんじゃねぇよ。
まあ、子供の頃は好きだったけど。この別荘抜け出して、水の底から月を見上げて」
空に三つの月が昇る週なんかは興奮したもんだ。
「ああ、月か。美しいな。太陽は少し光がきついが、月の光には魔力も宿る。
月の神ルノリアに会った事があるが、それはそれは美人だったぞ」
ルノリア。俺も知っている神だ。
どうも現実離れしてるよな、やっぱり。でも何でか素直に受け入れている自分がいる。
目を輝かせてあんまりにも楽しそうにディーナが笑うから、俺も笑いかえす事にした。
*
「遂にやったな、ディーナ」
ディルフォトス=グラーレンは、自室で椅子に座り込んで呟いた。
彼女の兄の親友であったディルフォトスが、彼女に出会ったのは彼女が生まれてすぐ。
その頃から彼女の兄はかなりの兄馬鹿だった。
愛情と呼べるものかすら疑わしい、ただの偽りの心を向けるだけの彼女の両親とは対照的で、その違いに驚いたものだ。
そんな彼がいたならば、そもそも起こる事すらなかっただろう今回の縁談。
彼女の意志を無視するのも甚だしく、しかも相手は乗り気と来ている。
ディルフォトスは出来る限りの事はしたが、相手は海神の大将、強引に縁談が決まってしまったのだ。
よりによって、彼女の従兄弟と。
血を濃くするとかなんだかいう理屈などは嫌いだった。現に障害のある神の子すら産まれている。しかもその障害、最もましなケースでも四肢の一つが失われているという、悲惨なものだ。
で、結局、彼女がここから逃げ出す気になれば脱出出来るよう、手筈を整えておいた。
そうしたら案の定、逃げ出した。
グラスに白ワインを注ぎ、中に向かって乾杯の仕草をし、今はもういない彼に呼びかける。
「お前の妹はなかなかやるよ。まあ、今後の展開が心配だけど」
何処かにいて、ディルフォトスの声を聞いているのだろうか。
「なあ、……ノクトナハト……」
*
「夜は俺の時間、か」
蒼い石を弄びながら、俺は呟いた。
夜。月が昇り、日が沈み、海は不思議に妖しく揺らめく時間。
この名の所為か、昔から不思議と恐くなかったのは確かだ。夜に出る盗賊達は別として。
しかし、そんな風に形容した奴は一人しかいなかったというのに。神は名に依ってその性質を持つから当然そんな考えになるのだろうが。
そんな風に思いを巡らした時、急にくしゃみが出た。
「風邪かな」
夏風邪は面倒くさい。早く寝よう。
*
『彼』は妹の事を考えた。
大切な妹。可愛く、美しく、聡明な。
『彼』は手の中のものをしっかりと握る。目をつぶれば、はっきりと妹の姿が頭に浮かんだ。
けれどその横に愛しい『彼女』の姿。
『彼女』は泣くだろうか。泣いてくれるだろうか。
……いいや。父の事だ、おそらく自分の死亡など、かくしてしまうに違いない。
「ナハト! お前、まさか……」
親友の声が聞こえる。
最後に妹の声が聞きたかったが、その親友も十分大事な奴だった。
「じゃあ、ね。ディル。………ディーナ」
『彼』は足に自らの暗き炎を放った。
自分の体が燃えてゆく。これで楽になるのだと思った。
この体を流れる忌まわしい血から、逃れられるのだ。
手の中の『これ』は、あっちまで持ってゆこう。
その思考を最後に、『彼』の意識はとぎれた。
*
あの夕焼けを見た時から、俺とディーナは段々と親密になっていった。
いっとくけど、恋じゃない。もっと別の感情が溢れてくる感じだ。それは好意というものの中に入り、幸せというものが増えたように思えるという、とても心地良い感情だった。
でも、何かを忘れている気がする。
何か、重要な事を。
「おーい、何自分の世界に浸ってるんだ」
真っ昼間にそんな事を海を見ながら考えていると、従兄弟であるサイハ=ツウォイル=ファルグスが俺の前で手を振って、自分の方へと注意を促した。
ラフなTシャツに革製の高級ベルト、これまた高級そうなズボン。
サイハは一応この国、ファルグスの王子であるが、何でか勉強その他をほっぽり出してこの別荘に『珍しい客』目当てに来てしまうあたり、ちょっとそういう自覚が足りないのではないかと思う。傲慢に威張り散らす奴らよりはよっぽど良いけど。
従兄弟で歳も近いので、多分一生付き合っていかなければならないのだから、そんな事をがみがみ言う気もない。間違って後々尾を引いたりするといやだし。
それにそんなサイハという男を俺は良い奴だと思っている。
「ああ、いや。
……ちょっとな」
何かを忘れている気がする、なんて言っても多分こいつは何も分からないだろうし。
「なーにが『ちょっとな』だよ。かっこつけやがって」
『ちょっとな』の所で俺の真似をしてあごに手を当ててサイハが抗議する。
「いいんだよ、別に」
そう言って微笑んでみた所で、俺はふっと気が付いた。
俺のディーナに対する感情は、サイハへのものととても似通っている。
そうか。そうだったのか。
分かった。このディーナへの気持ちの意味が。
「まさか、例の訪問者さんに恋でもしてるんじゃないだろうな」
「違う。そんなわけないだろ。
……妹。そんな感じだ」
「妹ぉ?」
お前そんな趣味だったの、と軽口を叩くサイハの頭をはたく。
「お前みたいなもんなんだよ。恋じゃない。それは確実に分かる」
海を見つめながらそう言うと、サイハがふぅん、とよく分かっていなさそうな声を上げる。
そしてその一瞬後。
「じゃ、その子は俺が貰うよ」
その言葉に俺は凍り付いた。
「……は?」
「一目惚れした」
「い、いやちょっと待て」
混乱する思考を強引におさめ、手をあげてサイハの言葉を止める。
「お前、恋人いたろ?
……それも二、三人じゃなく」
なにせ一国の王子様だ。自分用の後宮のような組織もある。
しかも結構な美形でプレイボーイときていて、俺はこいつの女がとぎれた所を見た事がない。
「別れる。もうその旨の手紙も出した」
早っ。
「だから、あの子、落とす。絶対に」
そういうサイハの瞳は真剣そのもの。
やばい。絶対にディーナはこいつに惚れてしまう。
そう思えば胸がざわざわする。嫉妬ではない。『兄』としての心配だ。
てか、
「ディーナって……親父と同じ顔だろ?」
「同じ顔でも、違う。表情も、性別も、全部」
「海神の、子だぞ」
「なんだよ。『兄貴』としちゃあ心配か?」
「まあ、そうなんだけど」
「酷いな」
俺ってそんなに信用無いの、とサイハが苦笑する。
「だってお前、二股三股当たり前だろ。そんな奴にディーナをやれるか」
「そう? でも大丈夫、今回は本気」
サイハはにかっと笑う。
「絶対に落とす。手に入れる」
軽そうな笑顔でも、瞳がとても真摯だったから、俺は黙り込むしかなかった。
*
夜の静寂が心地良い。
ディーナは一人、砂浜を歩いていた。
ナイトは来ない。どうしたのだろうか。
せっかく、昼に会った新しく来たというあの青年の紹介をして貰おうと思ったのに。
それに、ナイトはディーナの兄に雰囲気が似ていた。いっそのこと兄と呼んでしまいたいぐらいに。
あの夜、自らの炎で己が身を焼き尽くした兄。
何があったのかは知らないが、ただただディーナはとても悲しかった事を覚えている。
だって兄はとても優しかったから。
司るモノのないディーナとは違い、『夜』を司っていた、優秀な兄だった。
満月がディーナを照らす。澄み渡った夜空。
そう言えば、兄が死んだ日もこんな日だった、と思いを巡らそうとした時。
「や、お嬢さん」
静寂が、明るい声によって遮られた。
「……お前は」
「ああ、覚えてくれていた?
俺はサイハ。サイハ=ツウォイル=ファルグス」
昼間会った例の男が、にかっ、と明るく笑って歩み寄ってくる。じゃりじゃり、と砂を踏む音。妙にリズムが良かった。
姿が若干似ているものの、どうもナイトとは違うタイプだ。
「ナイトの従兄弟ですよ、ウェイルディーナ様」
愛想の良い笑みのまま、サイハはディーナの隣に座り込む。
それに合わせて、ディーナも座り込む事にした。
「つまり、君の従兄弟みたいなものかな。ナイトよりは年上だ」
「どうして私の従兄弟になるんだ?」
「君の事を、『妹』のようだ、ってナイトが言ってた」
妹。それは的を射た発言だと思った。
自分もナイトの事を『兄』のようであると思っているのだから。
「で、君はナイトが好き?」
「好き?」
「恋愛対象として」
「それはないな」
やっぱり、と言って更に笑う。
そしていきなり、サイハが真剣な顔になった。
「? サイハ?」
「じゃあ、さ……。
俺と、恋人として付き合わない?」
鼓動が一つ、大きく鳴った。
*
「成功してるし……」
「ん? どうした?」
俺の呟きが微かに聞こえたのか、ディーナがあっけらかんとした顔で聞いてくる。
で、その肩にはサイハが手を。
「……付き合ってるの? 二人」
「うむ。なかなか話が合ってな。
それに、ときめきもあったしな」
胸を張って応えるなよ。
「……ときめきあったの?」
と戸惑った顔でサイハ。
……いや、告白したのはお前じゃないの?
「何を言うんだ。ちゃんとあったぞ。その末に承諾したんだ」
恐るべし、サイハの手練手管。伊達に俺が知ってるだけで約二十人と付き合ってたわけじゃないな……。
「へへ」
サイハが照れくさそうに笑う。それが本物の笑顔だと生まれた時からの付き合いの俺には分かる。
成る程な。本気だというのは本当だったわけか。
「まあいいよ。とりあえず、朝飯でも食おう」
俺達はそのまま、居間に向かった。
向かおうとした。
だが、いきなり、廊下が『別の廊下』になった。
内装は変わらない。けれど、明らかに別の空間だと、分かった。
「……止まれ!」
後ろを歩くディーナ達を止める。
「どうしたのだ、ナイト」
ディーナが目を見開いて聞いてくる。
「誰の仕業か、分かるか? ディーナ」
振り向いてディーナに問う。
その後ろに、廊下に続く、通ってきたはずの広間はない。
「……え?」
「ここは『別の廊下』だ!」
それで俺の問うた意味が分かったのか、サイハとディーナの顔が緊張に引き締まる。
「おそらく、この技は、『道』を司るロードローザだ」
ディーナがそう言った時、その後ろに灰色の髪に海色の瞳をした女性が現れる。
「ははは。ご名答だ」
その女性はそう言うと、ディーナの首に小刀を当て、床に手を向ける。
ディーナと女性…おそらくロードローザの下に穴が開いた。
水底に通じる『道』が。
「……待て!」
そのまま二人は一緒に落ちてゆこうとする。
サイハと俺は咄嗟に手を伸ばす。行かせるものか。
その女性の灰色の髪にサイハの手が触れた。
けれど、それだけ。
穴の中に二人が消え、そのまま廊下は『廊下』に戻った。
「やられた……!」
俺の言葉と共に、サイハが、がくりと膝をつく。
「サイハ!」
「……畜生!」
サイハは顔を歪めて慟哭した。
*
ウェイルディーナロードローザに連れ戻された。
ディルフォトスはその一報に溜め息を落とした。
とりあえず、情報だ。
親友の妹であり、妹のような存在でもある。
幸いディルフォトスが彼女の脱走の手筈を整えた事はばれていないようだし。
(ロードローザに接触しておくか)
そう考えて、報せをもたらしてくれた部下にねぎらいの言葉をかけると、ディルフォトスはロードローザの領域へ向かった。
「あァ、ディルフォトス。
残念だったなァ」
けらけらと、ロードローザが笑う。
「ノクトナハトの妹はワタシが連れ戻したよ」
少し耳に触る低い声。
『道』を『絶つ』彼女の双子の妹、ロードサイアとは正反対である。
どちらもその美貌は見劣りはしないのだが、ロードサイアは穏やかで、ディーナの意に反する事など出来るような女神ではない。
ロードローザは彼女と違って、自分の為ならディーナを攫うぐらい糸も容易いのである。
「ああ。そうみたいだな」
ディルフォトスは指し示された椅子に腰を下ろす。
けらけらと、ロードローザがまた笑った。それと一緒に彼女の領域の壁が赤く変化する。
ここは彼女であって彼女の支配する所であるから、それはそうだろう。
だが、自分の『領域』の色が変化するのを隠しているディルフォトスにとっては、少しなじめない光景だった。
「簡単だったよ。けれど、……」
愉快そうに話し始めようとしたロードローザの表情が不機嫌な様相を呈する。
壁の色は、本人が不快と思っている色であろう、黄土色が映った。
「人間の分際で、ワタシの『別の道』に、気付いた奴がいたんだ。忌々しい。
まあ、ワタシの能力を止められる程ではなかったけどね」
「……へえ」
特殊な人間だったのだろうか。魔術師やら、巫女の家系などの。
「ディーナは『三界の命』の家にいてね。
『三界の命』は避けたっていうのに……」
それだけが玉に瑕である、という気分らしい。ロードローザが苛つくように灰色の髪を掻き上げた。
そこに一本だけ、色の違う髪がある。焦げたような赤黒い色。
「……? その髪は?」
「え?」
ロードローザが髪の存在に初めて気付いたようで、彼女は舌打ちをしてそれをピッと抜く。
「なんだこれ」
その髪はロードローザがそれを捨てようとした途端、発火して蒸発してしまった。
「熱ッ!」
「大丈夫か?」
「ああ、まあ。ちょっとまだ熱いけど……」
「そうか、よかった」
一応の社交儀礼をディルフォトスは言う。
少し赤くなったロードローザの指先は、治癒力のおかげで一瞬で元に戻った。
そして、暫くの沈黙。
ディルフォトスは、これ以上何も聞く事もないので席を立つ。
「じゃあな」
「ああ、じゃあ」
ディルフォトスはそのままロードローザの領域の、幕のようになっているところを通り抜け、ロードローザの領域を後にした。
あちらこちらにある神の『領域』が、それぞれ独特の色を発して廊下のようになっている中間の空間の両側にある。
この海の城の中にある『領域』はそれぞれの神の部屋のような物だ。所領を持つ神の部屋、つまり別の空間にある部屋とも繋がっている。それでいて、神の感情、生死などをを表す事もある。
神の部屋であり、神でもある、というのが、正確な所だろうか。
そういえばディーナが見てきた人間の家とは如何様な物か、と想像を巡らしつつ、ディルフォトスは一歩を踏み出す。
「あら、ディルフォトスさん」
その時、丁度別の領域から穏やかな声がかかった。
「ロードサイア」
「いかがなされました? ロードローザさんとお話をしていらっしゃったようですが」
丁寧で、決して耳障りではない声。
この声をディルフォトスは気に入っている。
「ちょっとね。ディーナの事で」
「そうですか…。ノクトナハト様の妹君ですものね。
……ところで、あの、お茶でも如何です?」
「ああ、じゃあお邪魔しようかな」
そう答えて、ディルフォトスがロードサイアの領域に足を踏み入れようとした、その時だった。
「ぎゃぁぁあぁぁあああぁぁぁあああァ!」
ロードローザの耳障りな声が背後から突然襲ってきた。
「……!? なんだ!?」
「ローザ!?」
ロードサイアが領域から走り出てくる。
ディルフォトスが振り向くと、ロードローザの領域が揺らいでいた。
そしてそのまま、黒く紅く染まる。
「熱いィ、熱いよおォォ、サイアぁ、あァ、ァ……」
そのまま、ぼん、とまるで炎が全てを焼き尽くしたかのような音を立てて、ロードローザの領域が崩壊寸前の状態になる。
その光景に、ディルフォトスは見覚えがあった。
「ローザあァァァ!」
ロードサイアがそこに向かって駆け出そうとするのを、ディルフォトスは自らの司る『海の砂』の山を発生させて止め、ロードサイアを羽交い締めにする。
「無理だ!
もう、助からない! 君まで死んでしまう!」
「いやあ! どうして、死ぬって決まったわけじゃないでしょう!?」
「死ぬ! 絶対にだ! あれは、」
ディルフォトスは一瞬言葉を止め、そして叫ぶように告げた。
「『夜の炎』だ……!」
死んでしまったノクトナハトのみが用いる、夜の色をした、最強の炎。
如何なる水でも消えない。ノクトナハトの意志のみが消せる。
その炎は、神すら燃やし尽くしてしまう。そして実際、助かった者はいない。ノクトナハト本人でさえも。
だから、ロードローザは助からない。
ここにはノクトナハトがいないのだから。
だが、ノクトナハト無しでは発生しようもない。
(ノクトナハト。今、何処に居るんだ)
何処で、妹に害をなした神を、燃やし尽くしているんだ。
*
燃える。燃える。そこにある全てが燃える。
燃えてしまえばいい。
燃えてしまえばいい!
そうして燃やしてきたのだ、己の汚れた体も!
ほら、燃えるがいい!
滅びるがいい!
夜に包まれて消えるが如く、
燃 え 尽 き て し ま う が い い !
「………」
俺、放火願望あるんだろうか。
燃え尽きてしまうがいいって……。あんた。
妙な夢を見た自分につっこみを入れつつ、枕元に置いていた蒼い石を弄り、まだぼんやりしている頭をはっきりさせる。
うん。なんか変な能力がついてるんじゃないか、と一時はまわりの大人をひやひやさせたこの石だけど、やっぱり落ち着く。
「さて、と」
ベッドから出て、立ち上がる。
横にはリュック。
一応、魔結晶に、お守りに、短剣に、とバラエティに富んだ物をつめてある。
なにせ、神様に喧嘩を挑むんだからな。
でも、不思議と緊張感は無い。相手があまりにも漠然としていて、圧倒的すぎるからだろうか。
そう思いながらもリュックを背負ったら、いきなりクシャミが出た。
「……誰か、俺の話でもしてるのかな?」