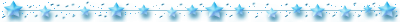目の前で、俺の護衛対象の王子、スイトが溺れていた。
乗っていた船の甲板から、突然の大波によって落ちてしまったのだ。
どうにか追いつけそうなものの、それまでスイトの体が持つかどうか。
それに、いくら俺でも同い年のスイトを抱えて泳ぎ切れるかどうか。
そんな状況だった。
だがしかし、その状況は一変した。
いきなり初めて見る少女がスイトの下から現れ、彼を抱え上げたのだ。
サファイアのような瞳に、亜麻色の髪。
真珠のような肌。
そして、本来ひとなら足があるはずの所に、魚のようなうろこ。
見間違いではない。
俺が見たのは、紛れもない、
―――人魚、だった。
信じられない。
俺は心からそう思った。
一体、なぜ、と。
今となっては一ヶ月も前の事を思い出しながら、俺は夜の海を泳ぐ。
海の水が冷たいが、そんな事どうだっていい。
・・・ちくしょう、ナナキの馬鹿野郎!
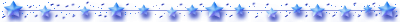
俺の名前はルイト=ツウォイル。
本名ではない。けれど、皆からはこの名で呼ばれている。
俺が探している彼女の名は、ナナキ。
あのとき、俺が護衛をしていたファルグス国のスイト王子が隣国を訪れ、嵐で宴会をしていた船から投げ出された時、助けた人魚だった。
一ヶ月前、俺が人魚を初めてみたあと。
彼女はスイトを浜にあげ、介抱した。
俺はその様子を気付かれぬようにしてみていた。
どうやって対処していいか分からないし、どうやらスイトはどうにか大丈夫のようだったし。
けれど彼女はスイトがぴくりと身動きすると、すぐ海へ入っていってしまった。
するとタイミングよくそこに、女性が通りかり、スイトに駆け寄ると、いろいろとスイトの様子を見た後、スイトをたたき起こす。
ファルグスの隣国、つまり訪れていた当地、ウォーレム王国の王女、サラ=レイティだった。
スイトは目を覚ますと、サラに言う。
「あなたは?」
「この国の王女、サラだ」
彼女はつややかな黒の髪に、意志の強そうな黒の瞳の十九,二十位の女性。
「俺を助けてくれたのか?」
ここで普通の女なら、それなりにかっこいいスイトの言葉にうなずくところだろう。
しかし。
「なにをねぼけているのだ、おまえは」
彼女はひと味違った。
「私が来たとき、すでにお前は誰かに介抱されていた。
とりあえず従者を呼んでこよう。ここに放っていくわけにもいかない。
城に連れて行くが、いいか」
彼女はずいぶんとぶっきらぼうだった。
「ああ」
スイトが答えると、
「そうか。ま、それまで休んでおけ」
ため息をつく。
「・・・ああ」
スイトは頷くと目をつぶり、あっという間に寝息を立て始めた。
変わった姫だと思っていると。
「おい、そこの男。事情を知っているのか?」
「え・・・」
「知っているようだな。とりあえずこいつについていろ」
「あ、はい」
ざくざくと歩いていく王女。
この俺に気付くとは。
別に自信過剰でもないが、彼女はなかなかの奴のようだった。
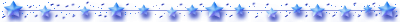
それだけだったら、俺はただの『不思議な体験をした人』で済むはずだった。
ああ。
何で、そのままで済まさなかったのか。
もう、後戻りは出来ない。
何故だろう。何故、彼女に、
・・・恋など、してしまったのだろう。
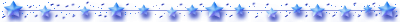
その翌日。
俺はスイトと一緒に、海岸を歩いていた。
「へ〜」
「信じてないな、スイト」
「うん。ルイトだろ、助けてくれたの」
ぁぁ、信じそうにもない。
「もういい。そういうことにしとけ」
この野郎が。
「おーい、スイトさん」
「はーい」
20トルガ(約15メートル)先から古参の衛兵のアルマーノ=ジョルッジオさん(50歳)から呼びかけられ、そちらを向く。
「この女の子が、あなた方に興味があるらしいですよ」
「は?
それはまた・・・」
その、アルマーノさんと話していたらしき少女を見た瞬間。
思考が、停止した。
サファイアのような瞳に、亜麻色の髪。
真珠のような肌。
しかし、昨日見たうろこはない。
その代わり、あるのは美しい足。
何ですかそりゃ。
信じられなかった。
昨日見た人魚が、人間になっているなんて。
一応服は着ているが、水着みたいなもんだ。
俺は彼女に近づき、スイトからは見えない岩場に引っ張っていった。
「・・・!」
話せないらしい少女がもがく。
「うろこは、どうした?」
そう言うと、目を見張って、そしておとなしくなった。
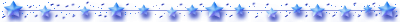
あの日、あのとき、あの場所で、彼女と出会ってなかったら。
誰かが、そんな事を言っていた。
けれどもう、出会ってしまったんだ。
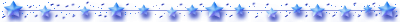
俺は、びしょぬれだった。
彼女も、びしょぬれだった。
そして、笑っていた。
何でこんな事になったのか。
岩場で彼女が足を滑らせて、俺がそれをかばって、そして浅かったけど、海に落ちた。
そして、彼女は何を思ったか、俺の顔に海水をかけてきた。
そのままムキになって水のかけ合いをするうちに、
こんなどっかの青春劇のワンシーン。
「お前、名は?」
「忘れた」
「話せたのか」
「うん。私が人魚って、何で分かったの?」
「お前が王子を助けた時、俺もあいつを助けようとして海に潜ってたから、見たんだよ」
「見られてたの!?」
「ああ。 お前、何で名前覚えてないんだ?」
「海の中では、そんなにお互い名前を呼び合う習慣がないの」
なんだ、それは。
「変だな、それ。……でもお互いを区別しなくちゃなんないだろ。どう呼ばれてたんだよ」
「七の姫、って」
「そんならお前の名前、ナナキにしようか」
「え?」
ふっと俺の心に浮かんだ名前。
「いい名だと思うんだけど」
「うん」
なんだか微妙な顔をして、ナナキが言う。
「でも単純」
「悪かったな。何でこんなとこに来たんだ?」
「王子様に、会いたくて」
「はぁ?」
なんとまあ酔狂な。
「あいつにだって?」
「うん。あの、話せば長くなるんだけど……」
そう言って、彼女はしゃべりだした。
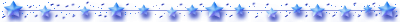
アホー、アホー。
カラスが鳴いている。
空が赤く染まり、太陽が地平線に沈みかけていた。
俺はふっ、とため息をつくと、言う。
「本当に長い話をするな」
「やっぱり?」
まったく。
彼女はかねてから陸の上の人間の世界に興味を持っており、ついにはその好奇心がふくらむあまりに俺たちの乗っていた船をのぞき込んだのだと言う。
王子としてそこにのっていたスイトは、護衛(俺)なんか気になんない程かっこよく見え、ナナキの好奇心をかき立てた。
そして、スイトに恋をしたと感じたナナキは、海の魔女の所に行き、人間になれる薬をもらった。
宝石10個を支払ったらしい。
そしてここからが重要。
その薬は、一ヶ月以内に恋が叶わなければ、泡になって消えてしまう何て言う、物騒なもので、その上陸に上がる理由になった者をはじめとして、だんだん人と話せなくなるらしい。
だから、どうにかして王子をゲットしたいから、会いに来た。
彼女の話を要約すると、こんな感じだ。
なのに何でこんなに時間がかかるのか。
とりあえず、ほっとくわけにもいかないし。
ふと、スイトのメイドが一人休んでいたのを思い出す。
あれ、いけるだろうか。
「しょーがないな」
ふぃ、とため息をつき、俺は立ち上がる。
「確かメイドの仕事があったはずだ」
「え……」
ナナキが期待に満ちた瞳で見上げてくる。
「やれるか?」
「うん!」
ナナキは、笑ってそう言った。
綺麗な、満面の笑顔。
それにどきりとし、自分が男である事を改めて思い知った俺だった。
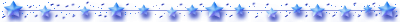
あのときの笑顔。
波に揺られつつ、思う。
泡なんかにさせない。
絶対に俺が見つけ出す。
また、彼女が笑えるように。
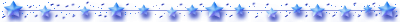
「ほらナナキ。美味しい美味しい果物〜」
「ちょっと、やめてよ!今仕事中なんだから……」
そう言う彼女の口に、ピーチを放り込む。
「……おいしい」
「そうだろ?」
「ってそうじゃないって!何でいっつもこんな事するの……」
「おやおや、いいんだけどねえ。ちょっとぐらい何か食べても」とメイド長。
「わたしがいやなんです!」
おお、真面目な。
すでにナナキが来てから一週間がたっていた。
ナナキはいつも真面目で、やる事はきっちりこなす。
そんなわけで結構人気があるのだが、何となく俺はちょっかいを出してみたりしている。
ナナキの反応は面白い。
「それに結構名物なんだよ、あんた達のラブコメ」
「そんなんじゃないですって」
これのどこをラブコメというのか。
そんな顔でナナキが言う。
それもまた、面白い。
「ああ、ナナキちゃんはスイト王子のファンだっけ?」
「違います、本当に好きなんです」
「ならルイト君、奪っちゃいなさいよ」
「ああ、スイトは相手にしないって。それに……」
ナナキは、スイトの前では話せない。
そう言いかけて、ぐっと口をつぐむ。
あと、三週間。
「とにかく、じゃね!」
ナナキはそんな俺の様子にも気付かないで、かけていってしまった。
「ねえ、ルイト君」
「なんですか?」
「あの子、本当にスイト君が好きなのかい?」
なじみのメイド長が言う。
「へ?」
「あれは、ただの憧れだよ」
「だからチャンスがある、とか言うつもりですか?」
「いいや。けど、何かあっちゃいけないからねえ」
「どういう事です?」
「どうやらね、サラ王女にスイト君、ほれちまったみたいだからね。あの子がかわいそうだと思ってね」
それは知っている。
しかも、サラ王女もまんざらではないらしい。
何でも、スイトはサラが正直にスイトを助けていない事を言ったのが気に入ったのだとか。
これはまさに、俺にとっては難しい問題だ。
スイトには惚れた奴と幸せになって欲しいし、それがサラ王女のような人ならなおさらだ。
しかし、このままではナナキが死ぬ。
「ねえ、聞いてんのかい?」
「あ、はい」
メイド長の声で我に返る。
「とにかくだ。あの子は憧れと恋を、勘違いしてるのさ。このニナ=ジョルッジオ50歳の経験をなめんじゃないよ」
「そうなんですか?」
「そういうもんさ」
どうだか分からないと思うけど、そうなのだろうか?
女心は複雑だ。
っていうか。
「メイド長、ニナなんて名前だったんですか?」
しかも。
「ジョルッジオって」
アルマーノさんの。(結構前の文章参照)
「ああ、知らなかったのかい? あたしゃああの人の妻さ」
うそぉ。
意外なところで、新事実、発覚。
「何で知らなかったんだ、俺」
「そりゃあまあ、あたしはメイド長ってだけで通してたしねえ」
そんな話によって、俺はニナさんがナナキについて言ったことを、忘れてしまっていたのだった。
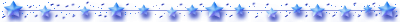
あのとき、どうして忘れていたのか。
そしてあの後、あのときどうして思い出したのか。
ナナキは、スイトに憧れてた。
それを今も気付いていないのだろうか。
とにかく、彼女を見つけ出さなければ。
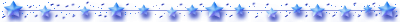
メイド長の本名が判明して、三日後。
「で? ナナキちゃんとは今のところどう?」
スイトに言われ、俺はスイトの方に顔を向けた。
「どうって・・・なんだよ。別に付き合ってるわけでもないし」
「そうか・・・いや、サラと賭けてるんだよ。“ナナキとルイトが付き合う”に俺が、 “付き合わない”にサラが」
「勝手に賭けるなよ」
そう言いながら俺は俺たちがいる部屋を見渡す。
綺麗な木製のテーブルに、その上に置かれたトランプカードセット。
「誰かくるのか? サラ王女とか」
「うん。サラとナナキちゃん。ナナキちゃんトランプ知らないんだって」
はい?
「ナナキが?」
「そう」
ちょっと待て、と言いたい。
「優しく教えてあげてね」
「おいおい・・・」
ナナキは俺じゃなくって、スイト目当てに来るんだって。
そう言いたいのをこらえ、俺はドアの方に近づいた。
その時。
四方八方から、殺気。
「おい……」
腰の愛剣『無銘』を抜き、俺はスイトに声をかける。
「うん。どこの奴らかな」
「さあな、とりあえず……」
天井から飛び降りてきた例にもれず黒装束の男を切り捨て、俺は言った。
「雑魚だ」
タンッ、タンッ、タンッ。
黒服の男達が次々と現れる。
スイトも剣を抜く。
俺は皮肉げに笑いながら、思う。
さあ、楽しい楽しい、ショーの始まり………
となるはずだった、が、
「しつれいしまー…… え?」
ドアが開き、ナナキが入ってきた。
やばい。
反射的にそう思う。
「逃げろ!」
「え、ぁ、っ………!」
ナナキは身を翻して走ろうとしたが、その目の前に黒服の男が降り立つ。
そして、ナナキに拳を繰り出す。
考える暇はなかった。
気が付いたら、護衛対象であるはずのスイトをおいて、ナナキの前に駆け込んで、そして黒服の男を斬っていた。
それ以降は、うっすらと覚えているものの、記憶にない。
ただ、最後にこう思った。
ナナキは、無事かと。
俺は、死なないだろうから。
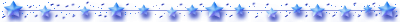
−−−お母さん、あの子と遊んでいい?
ああ、これは、昔の記憶だ。
−−−駄目ですよ。あの子とは、身分が違うでしょう。
身分? ほんとうに?
−−−あの子はね、神様の祝福を受けたのよ。
祝福?
こんなものの、どこが。
本当は、忌まわしいと思ってるんだろう?
祝福とかいいながら。
−−−だから、あっちにいきましょうね。
俺は、小さい頃にスイト以外と遊んだ記憶がない。
いや、あってもばれたら、すぐに引き離された。
やっと公に友達が出来たのは、7,8歳の時。
それまで俺は、遊びたい奴とも遊べず、毎日のように武術の訓練をしていた。
祝福。
神が与えたという、祝福。
それは果たして、祝福なのか?
俺にとって、それは烙印以外のなにものでもなかった。
忌まわしい。
祝福と言いながら、大人達は俺を化け物でも見るような目で見ていた。
祝福の子。
それが俺に付けられた名前だった。
−−−はぁい。じゃあスイト君とならいいでしょ?
記憶が、再現される。
たぶん俺は夢を見ているのだろう。
目の前を去っていく子供が振り返り・・・
その、顔は。
・・・ナナキっ!?
ばちっと目を開け、俺は飛び起きた。
ちくりと腹に小さな痛みが走る。
腹に丁寧に包帯が巻かれていた。
「ちょっと・・・! 起きたと思ったらどうしたの?」
「ナナキ」
ナナキが横に座って、ベッドの上の俺を見ていた。
「・・・まだ動かない方がいいと思うけど」
「別に大丈夫だって」
「え? だってあんなに大きなケガしたじゃない」
「もう治りかけてる」
「あれだけ大きな傷が、治るわけ」
ばりっと包帯をはがし、ナナキにそこを見せる。
思った通り、それはもう治りかけていた。
わずかに小さな傷があるだけ。
「うそ、だってあんなに大きな」
「俺はそう言う体質なんだよ。すぐ傷が治る。致命傷でも食らわない限り」
「そんなことってあり?」
と言いながら、ナナキは傷を確かめる。
「・・でも」
「ん?」
「ありがと」
「え」
「それでも死ぬ可能性はあったんでしょ? だから、守ってくれてありがとう」
ありがとう。
スイト以外に言われたことのない言葉。
いつもは、当然だとばかりに言われなかった言葉。
「おう」
そう言って、笑う。
ナナキは何故か少し顔を赤くすると、言う。
「憎まれ口たたくかと思ってたのに」
「なんだよそれ」
「じゃ、もう仕事に戻るわね」
「ああ」
そう言って立ち上がったナナキに、俺は言った。
「知ってるか? 俺みたいな奴の呼び名」
「ううん」
「『祝福の子』っていうんだ」
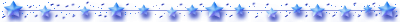
その時からだ。
俺が、彼女をいつの間にか目で追い始めたのは。
そして、もっとよく話すようになったのは。
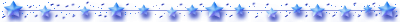
「よ、ナナキ! 何か食いに行こうぜ」
「だめ! 仕事があるんだから!」
いつも彼女は、真面目だった。
「ルイト、ちょっと。少し分かんないんだけど・・・」
そう言って一生懸命な顔を見せ、時には
「はい、これ、おすそわけ!
ニナさんがくれたんだ」
なんて、果物を差し出して笑ってる。
ただそれを見るだけで、幸せに慣なれた。
けれど本当はそんなことを思う場合ではなかったのだ。
黒服の襲撃から、五日たち。
俺はスイトから、スイトとサラが結婚することになったと伝えられた。
ナナキの死の期限まで、およそ二週間となっていた。
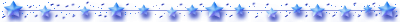
そしてその次の日。
「どうしたの、ルイト」
城の廊下で、スイトの部屋から出てきたところのナナキが俺に話しかけてきた。
「・・・いや」
なぜだか少し、ナナキの目が赤い。
「目、・・・赤いぞ」
「あ、ちょっと寝不足で」
「そうか?」
「うん、そうそう。
ね、・・・その」
「なんだよ」
「ううん。あ、王子様から本もらったんだけど、字が読めないんだ。
読んでくれない?」
「いいけど。そのうち勉強するか?」
「うん。一応勉強はしてるんだけど、なかなかね」
「さすがだな」
「何か最近、ルイト素直になったね」
「は?」
「いや・・・なんとなく」
「そうか?」
まあ、確かにそうかもしれない。
ナナキといるとなんだか幸せで。
ついつい思ったことをいってしまう。
そうだ。
俺が文字を教えようか。
そう思った時。
と、ナナキが手を合わせてこういった。
「あ、スイト王子に習おうか!」
「・・・え」
「そうだ、そうすればもっと親しくなれるし」
「いやでも、あいつ忙しいだろ」
「でも、さっきサラ王女と二人で教えてくれるって」
そう言って笑う彼女を見ながら、俺は胸の中のどす黒い感情が、広がっていくのを感じた。
「・・・あの二人、婚約したんだぞ?」
「え・・・」
ナナキが驚く。
むかつく。もの凄く。自分勝手かもしれないけど。
「知らないのか?」
好きだからだと。
・・・お前、失恋決定だな」
このままだと、お前の薬の効果はきれない」
自制が、きかなかった。
「・・・何で、そんなこと言うの」
「は?」
「ルイトの馬鹿!
黙っといてよ、そんなこと!
しかも・・・何で私の薬のことなんか言う・・・!」
きしっ。
彼女ののどが、妙な音を立てた。
「おい・・・!?」
しかし、彼女はそれでもなお、怒った顔で何かを言おうとする。
むかついた。
「お前なんか・・・
勝手に泡にでもなってろ!」
ひどい言葉を、はいた。
それから。
彼女とは一言も交わしていない。
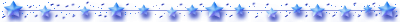
ごめん。
何度謝っても足りないだろう。
今、どんな気持ちでいる?
暗い海の水をかき分ける。
どうか。
間に合ってほしい。
彼女が泡に、なるまえに。
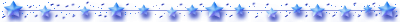
やっぱり、謝ろう。
ナナキが泡になるはずの日。
そこまでこないと、ふがいないことに決心がつかなかった。
くしくもスイトとサラの結婚式が船上で行われたの夜に、俺はそう決心し、それを伝えるために船の中のスイトの部屋に行った。
それをスイトに言い、現場を離れるためだ。
しかし扉を開けてその時、信じられない光景が目に入った。
ナナキが短剣を振りかざし、寝ているスイトを刺そうとしていたのだ。
「ナナキ!? 何を・・・」
「・・・っ」
ドン、と俺にぶつかり、ナナキは走り出ていく。
「ちょ・・・!」
「ルイト、そんなところにいたか!
早くナナキを助けろ!」
ナナキがかけていったのと反対の方から、女性の声。
「サラ王女!?」
「ナナキの姉が来て、これにスイトの心臓の血を吸わせろとあの短剣を渡したのだ!」
「え!?」
「私は偶然それを見ていたのだ・・・早く!」
サラはスイトの安否を確認すると、俺と一緒に走り出す。
そして俺が見たものは。
甲板から飛び降りる、彼女の姿。
「ナナ・・!」
すぐさまそこに駆け寄ってしたを見るが、そこには暗い海と
−−−6人の人魚。
「おい、お前ら・・・!」
「あなたが私たちの妹をたぶらかした王子か!?」
「何!?」
「魔女に言われたのだ!
王子が七の姫以外の女と結婚するから、魔法を解くためにあの短剣をナナキに渡し、それにファルグスの王子の心臓の血を吸わせろと!」
なんだって!?
そんなにナナキは、追いつめられていたのか!?
しかし、そう思うと同時に。
引っかかるものがあった。
もしかすると。
「確かに・・・ファルグスの王子の心臓の血、と言ったな?」
「ああ!」
「まさか貴様・・・!」
サラが俺を見て叫ぶ。
その時俺は、もう海に飛び込んでいた。
いける。
そう、思った。
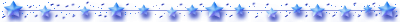
そしてやっと、ナナキを見つけた。
手には短剣、そしてだんだんともろくなっていくからだ。
もう意識も薄いらしい。
この可能性に、賭けるしかない。
俺はナナキのそばまで泳ぎ、ナナキの短剣に手をかける。
好きだからこそ、出来ること。
その前に、少しだけいいよな。
そう思い、ナナキの唇にキスをする。
そして俺は、短剣を、
自分の心臓に突き刺した。
鈍い痛みが広がる。
もしかしたら。
これでナナキは助かるかもしれない。
小さい頃の思い出がよみがえる。
昔、母さんに言った言葉。
−−−何で、ぼくだけ遊んじゃ駄目なの?
−−−ぼくだって、このファルグス国の
−−−王子なのに!
そして、ニナさんの言葉も。
−−−あの子は憧れと恋を、勘違いしてるのさ。
それなら。
ナナキがそんなことで死ぬのは、馬鹿らしいと思った。
命一つぐらい失っても、いいと思った。
どうか、彼女が泡にならずに済みますように。
俺の命なら、いくらでもあげるから。
好きだ、ナナキ。
意識が遠のいていく。
しろい。
しろいどこかへ。
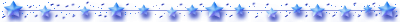
ごぽっ。
妙な音を立てて、口から水が出た。
一番に目に入ったのは、ナナキが目を真っ赤にし、泣いている顔。
それが徐々に驚きに変わっていく。
「ルイト・・・何で生きてるの?」
「ううわ、ごほ、ひど・・・」
「ちょっと、私の涙を返しなさい!」
「無理無理」
その原因をまず聞けよ。
砂の感触がした。
どうやら、砂浜らしい。
「ああもう、そうでした!
三つの命、だっけ? ああもう、知ってたのに!」
あらま。
「知ってたのか」
「うん。だけどさすがに心臓に短剣なら死んじゃうんだ、って〜」
また、ナナキの瞳から涙が流れ出す。
祝福の子の、もう一つの体質。
三つの命を持つ。
つまり、三回死なないと死ねない。
早い話、俺は後二つの命があるので、今回は死ななかった。
妙な話だ。
そう思う。
「あー、俺もそう思ったんだけどな。
三つの命の話も迷信だと思ってたし」
「そう? ルイトって夢がないよな」
「やかましい。っていうかおまえは信じてたのかよスイト」
「うん。ま、生きてて良かったよ。仮にも兄弟だしね」
それなら人の話を立ち聞きするな、弟よ。
・・・!?
「お、お前らいつの間に!?」
するといつの間にかサラと一緒に立っていたスイトが、
「んー? サラがルイト兄さんが海に落ちたって言ってきたから捜してたら、ナナキちゃんが兄さん抱えて泳いでくからさー」
「ってうそ!? 二人って兄弟だったの!?」
「ああ。ま、俺は祝福の子って事もあって、王位継承権無しだがな。一応、ファルグスの王子だ」
「なるほど。だからお前はあんな無謀なことをしたのだな」
サラが頷く。
「知ってたんじゃないのか?」
「いや、何となくだったからな」
「じゃ、ルイトがあの短剣刺したのって」
ナナキがへたり込む。
「あー、もしかしたら俺の血でもいいかなあ、と」
「いやちょっと。だからってこんな心臓に」
「俺がいいと思ったんだから、いいだろ」
そう言うとナナキは言葉をうっと詰まらせる。
そして深呼吸し、
「ありがとう」
と言う。
「ああ・・・べつにいいよ。
こんなに祝福の子で良かったと、思ったことはないから」
ケガの治りが早いだけなら、あんなに差別みたいなものを受けなかった。
命が三つもあると言われていたから。
皆がそれだけで、嫉妬混じりの化け物を見るような目で見た。
スイトや、他の変わり者たちだけだ。
俺を普通の人間として扱ってくれたのは。
「ルイト兄さんって、かなり苦労したからねえ。
正妃の子なのに、祝福の子ってだけで王位継承権無くしたし。
俺は、妾の子なのに、それがあって」
「別にそれは辛くはなかったぞ?
ただ、他の奴らの目がな、言ってたんだよ、化け物だって」
あの、冷たい瞳で。
「ふむ。苦労したんだな」
とサラ。
「まあな」
その時、ぽた、とあたたかいものが手に落ちた。
ナナキが、俺のそばで泣いている。
「おい、どうしたんだよ」
「さあねえ。前もナナキちゃん、泣いちゃったよね。俺がルイトのことと、祝福の子のことを教えた時」
なに!?
「なんだよそれ!?」
「後で聞けば? 愛しの彼女に、ねー」
「え・・・」
ナナキが泣き止み、こちらを見る。
なんて事を言ってくれるんだ、スイト。
けれど、確かにそれは当たっている。
俺は腹をくくり、ナナキに向き直った。
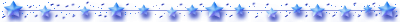
それから。
俺の告白は何故か見事に成功した。
何か後で聞いた話によると、ナナキはスイトを刺そうとした時、俺の事が頭に浮かんで、それで俺の事が好きという事に気付いたということで。
ちなみにナナキは目が腫れていた時、その前にスイトに色々と俺の置かれていた立場を聞かされていたらしい。
で、泣いたと。
同情か何か分からないけど、泣いてしまったのだと。
そう、言われた。
そこで思わず涙をこらえたのは、秘密だ。
いつか、ナナキに話すかもしれないけれど。
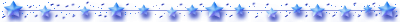
そして今、俺は自分の国、ファルグスの王城の一室にいる。
これから、俺を祝福の子とか区別しなかった奴らに、ナナキをお披露目する。
多分ナナキをナンパすると予想できる奴とか、酒が入るとどっかのマイナーな方言を使う奴とか、そんな奴らばかりだ。
けれどいい奴らなのだが。
「ルイト兄さん、まだサラが時間かかるって」
「おう」
サラはナナキを美しくするのだと言って張り切って控え室に連れ込んでいる。
「しかしまあ、ルイトに彼女が出来るとは。しかもロマンチックなラブストーリー付き」
「いい子? おとしてもいい?」
「うふふ、美しさでは負けなくってよ」
なんて声がここに集まった者の中から上がる。
「お前らな・・・」
「先に祝杯を挙げるとするか」
「おい!」
「いーねえ、それ」
スイト、お前も頷くな。
「ハイ、兄さん」
グラスを渡され、受け取ってしまう俺。
仕方がないか。
「では」
皆がグラスを掲げる。
俺もそれに習う。
「乾杯の声は、お前があげろ」
そう言われた。
何に乾杯しよう?
愛すべき弟。
この、愉快な奴ら。
俺の体質。
いろいろある。
けれど、やはり一つしかない。
こいつらには分かるだろうが。
俺は決めると、声を張り上げた。
「人魚の姫に、乾杯を!」
いつまでも一緒にいたいから。
ナナキ、君に乾杯を!
+++THE END+++